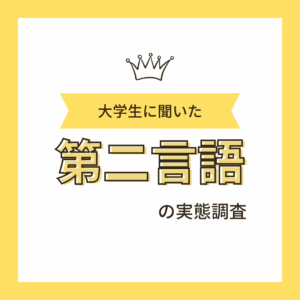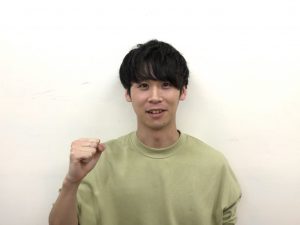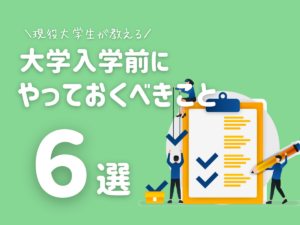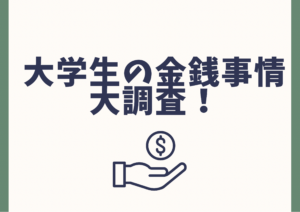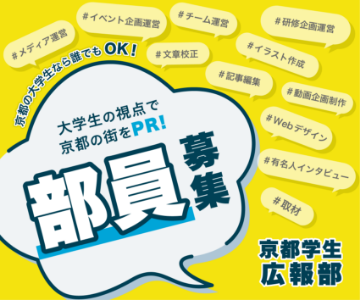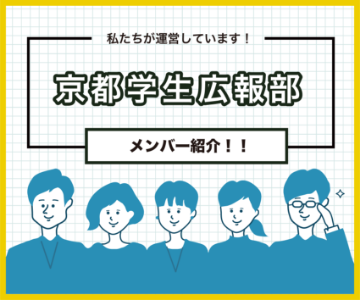桝太一さんインタビュー~アナウンサーから研究者へ~
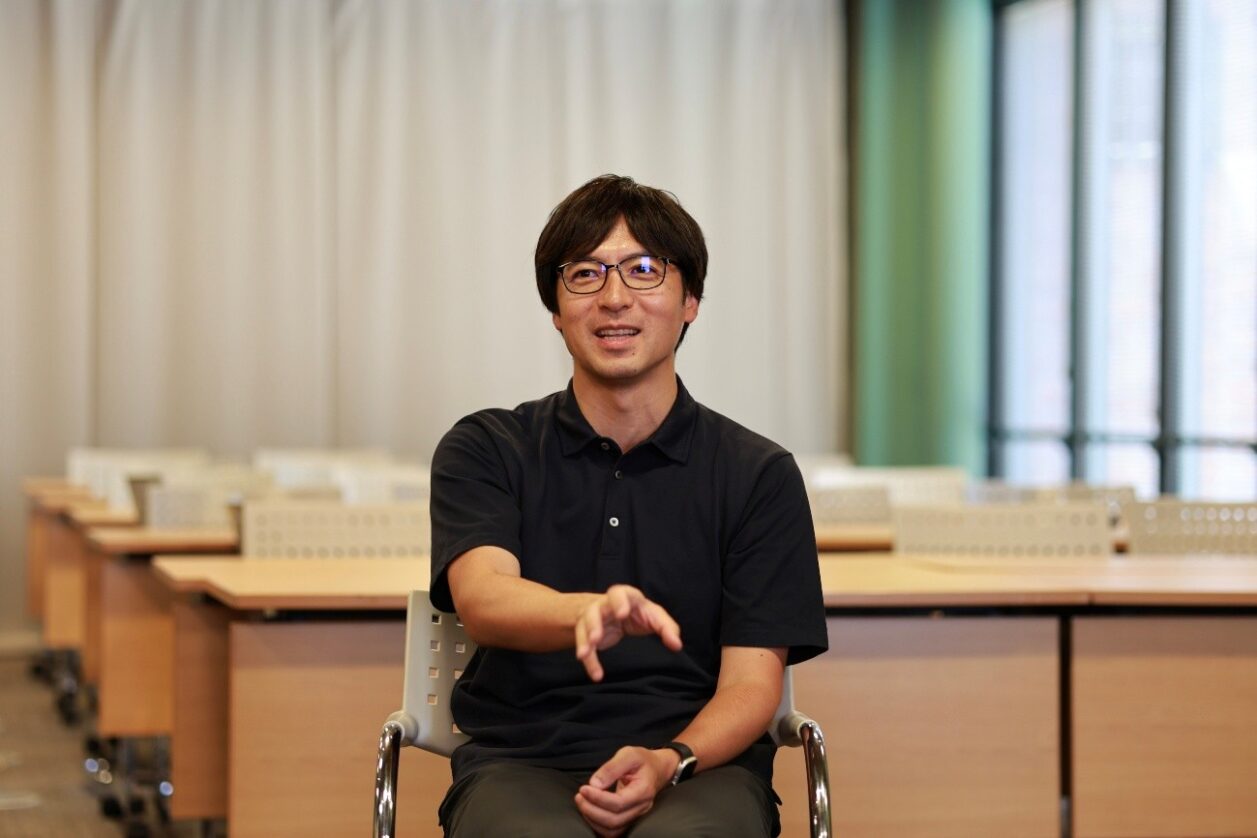
“桝アナ”の愛称で親しまれ、多くの視聴者に様々な情報を届けてきた桝太一さん。日本テレビを退職され、現在は、同志社大学ハリス理化学研究所の助教として活動されています。サイエンスコミュニケーションをテーマに、「テレビで科学をどう伝えるか」について研究されており、大学で講義も担当されています。
今回は、アナウンサーから研究者へと転身され、異色ともいえるキャリアを歩まれている桝さんにインタビューを行いました!
もくじ
科学好きの大学生からアナウンサーへ

―大学では農学部で主に海洋生物について研究されていた桝さんが、アナウンサーになろうと思われたきっかけはなんでしょうか?
桝さん:もともとは研究者になりたいと思って理系に進んだのですが、研究の世界はそう簡単ではなくて。僕なんかよりも一生涯を研究に捧げられるような人が周りにいっぱいいたので敵わないと思っちゃったんですよね。そこで「自分は研究する側ではなく、研究を伝える側に回ろう」と思ったんです。その方が自分の力を発揮できるのではないかと考えましたし、科学者と関わりながら新しいことを学べることも魅力でした。
それもあって、出版社やテレビ局、新聞社といった“伝える仕事”を中心に就職試験を受けようとしていました。
伝える側に回れたら、自分の持っている能力が研究者よりも活きるのかなと思ったんです。
―科学好きの視点で生きてこられた桝さんですが、アナウンサーになるにあたって「研究者の視点しか持たないこと」への危険性などは意識されるのでしょうか?
桝さん:そうですね。研究者の世界にいると、どうしても言葉や感覚が専門的になってしまいます。例えば、研究者は概要という意味の“アブストラクト”を“アブスト”と略して普通に使いますが、一般の人には伝わりません。
僕もテレビで「CO2が…」と口にしたときに、スタッフから「専門用語を使うな」「バカにしているように聞こえる」と指摘されたことがあります。そのとき、「二酸化炭素」と言えばよかっただけなんですよね。
専門に染まりすぎると、一般の人とのコミュニケーションが取れなくなっていく。そのギャップはすごく大きいと感じました。
―そのギャップを埋めるために努力されていることなどはありますか?
桝さん:テレビは「誰にでも分かる表現」を徹底して追求しているメディアだと思います。特に民放テレビは広告収益で成り立っているので、多くの人に見てもらわなければなりません。そのためには最大公約数をとる必要があって、難しい言葉を避け、小学生にでも分かる説明を目指します。
実際、僕が今の研究でテレビ局のディレクターに話を聞いたときも、「小学生に伝われば、中高生も大人も理解できる」という基準で番組を作っていると伺いました。それはすごく正しいと思いますし、分かりやすさを磨くための努力は、テレビから学んだ大きな財産です。
誰でも分かるようにすることがテレビ局の責務だし、結果それが科学をいかに分かりやすく伝えるか、という努力に繋がっていると思います。
アナウンサーから研究員へのキャリア転換

―アナウンサーから研究員になったきっかけは何ですか?
桝さん:アナウンサーは基本的に「伝える役割」なんですが、伝える相手である視聴者にうまく届いていないな、と感じることが多かったんです。特に東日本大震災やコロナ禍では、科学をどう伝えるかという場面で強いもどかしさを感じました。そもそもテレビの伝え方ってこれでいいのかな、と疑問を持ったんです。
自分には理系のバックグラウンドがあり、アナウンサーとして多くの経験もある。この立場なら、「テレビという媒体で科学がどのように伝えられるべきか」という研究ができると思い、転職を決めました。
―大学時代の研究と今の研究は分野が違いますよね。抵抗はありませんでしたか?
桝さん:いや、めちゃくちゃ苦労しました(笑)。大学で学んだ農学の知識があまり役に立たなくて、社会学の教科書を買ったり、社会学部の先生の授業を聴講させてもらったりして社会学はゼロから勉強し直しました。別分野に行くことは大変ですが、新しいことを学ぶ楽しさもありましたし、以前の知識が別の形で活きてくるのも面白かったですね。
―具体的にはどのようなことが活きていますか?
桝さん:科学を伝えるためにはまず科学を理解していなければなりません。僕は大学院まで最低限の科学のことを学んできたので、その理解をベースに「どう伝えるか」を考えることができます。これは全く科学のバックグラウンドがない人には難しいと思うんですよね。これは理系出身の強みであり、人文系の研究に移ったメリットだと思っています。
今後のテレビの在り方
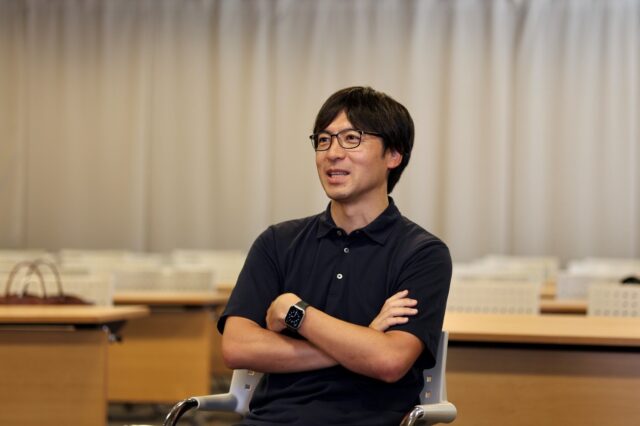
―今後のテレビはどうなっていくと思いますか?
桝さん:僕の研究は、「テレビを通して、科学がどう伝わるか」がテーマです。今の時代にあえてテレビ?とよく言われます。確かにSNSやネットが主流で、テレビは衰退していくと言われがちですが、僕は逆に「今だからこそテレビが必要」だと思っています。
SNSやネットはアルゴリズムで動いていて、興味のある情報しか目に入らない。つまり、興味がない情報には触れなくなってしまうんです。科学はその最たるもので、淘汰されやすい。そんな中で唯一、興味がなくても全員が同じ情報に触れられるのがテレビなんです。だからこそ、テレビの社会的な責務は今後むしろ増すと思っています。
―今後もテレビで伝えていきたいですか?
桝さん:伝え続けていかなければならない、と思っています。社会に共通の理解基盤があることは大切です。もちろん「好きな物だけを選んで生きる」ことも1つのあり方ですが、僕はやっぱりテレビの役割は残すべきだと思いますね。
京都の魅力

―京都を学びの拠点にするメリットは何ですか?
桝さん:京都に来て1番驚いたのは「五感が刺激される街」だということです。僕は千葉出身なので、京都は街中で山も川も見えることが衝撃でした。山の色も変わるし川に住む生き物も変わるので、すべてが五感を刺激してくるんですよ。こんなにも街そのものに自分を刺激する要素の多い街って他にあるのかなと思います。それが京都を選ぶ最大のメリットだと思いますね。
後は、自転車で走りやすいこと。京都は平坦なのでどこでも自転車で行けるし、鴨川沿いを散歩するだけでも面白いです。アオサギとかが普通にいたりして、毎回びっくりしています。
学生時代

―大学生の時はどんなことに力を入れて、学生時代を過ごしていましたか?
桝さん:1,2年生の頃は遊んでばかりいました(笑)。生き物が好きなのは変わらず、スキューバダイビングのサークルに入っていました。長期休みには、八丈島で住み込みのアルバイトをしていました。食事を作って、トイレ掃除とかも全部して、お客さんを送るといった仕事をする代わりに海に潜らせてもらえるというバイトがあって、働きながら潜っていましたね。
大学生のうちにした方がいいこと
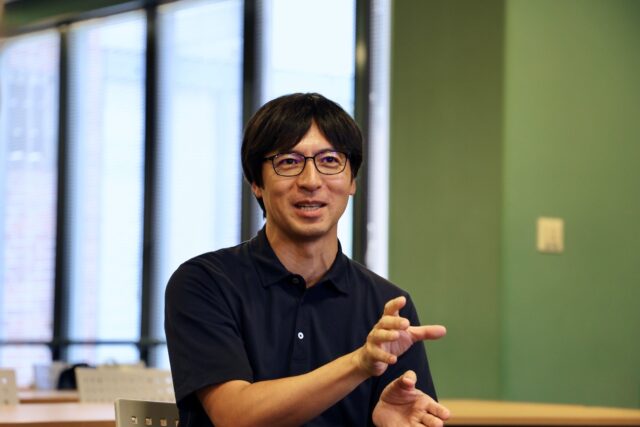
―大学生のうちにしておいたほうがいいことはありますか?
桝さん:社会人になると長期間の何かってできなくなるので、長期間かけてやることに挑戦してほしいですね。留学でも旅行でも、あるいはなにか1年間を通して取り組むことでもいいです。
もう1つは、失敗できる挑戦をしてほしいです。社会人になると失敗が結構尾を引くのでチャレンジしづらくなるのですが、学生の失敗は大きな糧になるので。
―ちなみに桝さんの失敗って何かありますか?
桝さん:たくさんありますよ。例えば、僕は大学時代、サークルのキャプテンをしていましたが、自分のせいでまとまらず、はっきり言って人間関係の構築に失敗しました(苦笑)。未だにそのサークルの人たちには「お前のせいで…」と言われますが、この経験から学んだことは大きいですね。
あと、親孝行は学生のうちにしたほうがいいです。僕は大学院修了時に母親とモロッコ旅行に行きました。モロッコで大げんかもしましたが、今ではいい思い出です。
自分の軸と好奇心を持つ!

―農学部からアナウンサー、研究者へと進んでいかれましたが、進路の決断の軸になった部分があれば、教えてください。
桝さん:僕の軸はずっと「科学・生き物が好き」ということです。周りから変わったキャリアパスだと言われますが、自分の中では一貫していると思っています。生き物が好きだから大学や大学院で研究をして、生き物のことを色々伝えたい、ロケに行きたいからアナウンサーになり、研究者になりました。職業は枝葉で、軸さえあればいろいろな形でつながるんです。
スポーツ好きな人が、選手だけではなく解説者や用具メーカーなど多くの道に進めるように、軸さえあれば職業の選択肢は広がります。損得勘定ではなく「心からやりたいこと」を軸にすることが大事だと思いますね。
―社会に出て、自分と違う人と関わる時に意識していることはありますか?
桝さん:1番はその人は自分の知らないことを知っているというリスペクトを持つことです。僕は好奇心が強いタイプで、知らないことを教えてもらえるのが楽しい。
僕は、タクシーの運転手さんとよく喋るんですが、自分が知らない面白い話をたくさん聞くことができます。京都で言うと、「最近は外国人の方多いですか?」とか「言葉とか通じないと困るんですか?」みたいなことを聞いちゃいます。そうすると、面白いことがガンガン返ってきて、「そうだったんだ。」という話がたくさんありますね。
大事なのは、「その人にないものではなく、その人が持っているものを見に行く」という姿勢。講義でも「僕から教えるだけでなく、君たちからも教えてほしい」と伝えています。結局、知らないことを知りたいという単純な好奇心なんですよね。
悩みを抱える大学生へ

―先ほど「好奇心が大事」「好きで進んでいくことが大事」というお話がありましたが何かにチャレンジする時、先々のことを色々考え、結局、無難だけれど、あまり興味がないものを選択してしまうことがあります。自分にとって興味のない分野にチャレンジする場合に、に何かアドバイスはありますか?
桝さん:まず大前提として、先を見通すことはすごくいいことなんです。それはむしろ才能だと思っていい。ただその分、「枠からはみ出せなくなる」こともあります。
そんなときのコツとして、僕がおすすめしているのが、“自分でランダムを作ること”です。例えば本屋さんや図書館に行って、目をつぶって1冊本を取ってみる。そして「この1年はこの本のテーマを徹底的に調べる」と決めるんです。
ぼんやり歩きながら「えいっ」と本を取ると、『トマトのすべて』みたいな自分にとって一見どうでもいい本だったりする(笑)。でも、それをきっかけに学んでみる。これはある意味、自分で「ランダマイズ」しているんです。インターネットだとなかなかできない体験ですよ。
大事なのは、ランダムを経た後は「決め打ち」にすること。「どんな本でも1度で会ったら1年やり抜く」と決める。そうやって強制的に枠を壊すんです。
もっと言えば、大学に貼ってあるアルバイト募集をダーツで決めて応募してみるとか、親御さんにシャッフルした求人票から1枚引いてもらうとか。それくらい「自分をランダムに委ねる」くらいでちょうどいいと思います。僕自身もそういうことを何度もしてきました。特に学生時代は、あえてそういう選択をするのもおすすめですね。
それから、将来を考えるときの僕の人生訓をひとつ。研究者になるか、アナウンサーになるか、みたいに「2つの道で迷う」時ってありますよね。その時に「どっちが成功するか」では選ばない。僕は必ず「どっちに行っても後悔する」と思うようにしてるんです。
「どっちの後悔なら自分が納得できるか」で選ぶ。ちょっとネガティブに聞こえるかもしれないけど、この方が気楽なんですよ。結局うまくいかなかったとしても、「自分で選んだ道だから仕方ない」と思える方を選ぶ。そうすると1歩踏み出しやすくなりますよ。
―小さい頃から理系の職業に就きたかったのですが、文系の勉強の方が得意で、理系の道を諦めてしまい将来にとても悩んでいます。同じような悩みを抱えている人にアドバイスはありますか。
桝さん:あくまでこれは「僕という1人のサンプル」の体験談ですが、文系か理系かよりも、「好きな方」で進路を選んだ方がいい、とずっと思っています。
成績的には文系が得意だけど、気持ちは理系が好き、というジレンマってありますよね。でも結局、長い人生で最後に自分を支えてくれるのは「好きなこと」なんです。
社会人になると理不尽なことや努力が報われないこともたくさんあります。その時に、「自分が得意だから」という理由だけで選んでしまうと、そういう時に折れてしまう。でも、「好き」は折れないんですよね。「自分は好きなことやっているしな」と思うことができれば、しんどい時期もくぐり抜けられるんです。
皆さんから見ると僕はテレビ局で楽しそうに働いていたように見えるかもしれません。でも実は、最初の3~4年間は地獄のようでした。
科学を伝えたいと思って入社したのに、配属はプロレス担当。血が大嫌いなのに。お笑い番組の前説を3年間やっていた時期もありました。理系の大学院でアサリの研究をしていた僕が、100人近い観客の前で笑いを取れと言われる。金曜は会社に行くのが本当に嫌で、まるで登校拒否みたいでした。
「こんなことするためにアナウンサーになったんだっけ?」と当時は何度も思いましたが「科学を伝えることが好きだ」という気持ちがあったからこそ、なんとか踏ん張れたんです。やっぱり「好きなこと」が力になるんだと思います。
今、文系か理系かで迷っていて、「理系が好き」だと思うなら、そこを基準で選んだ方がいいと思います。必ずしも研究者にならなくてもいい。大学院から理系に進む道もあるし、理系関係の出版社に就職する道もある。どんな形でも、「自分の好き」に関わっていることができる方が、長期的にみると幸せなんじゃないかと思うんです。
もちろんこれは僕1人の意見で、他の人の経験もぜひ聞いてほしい。でも、少なくとも僕にとっては「好き」を選んできたことが支えになっています。
おわりに

皆さん、いかがでしたか?
桝さんのお話を聞きながら、私自身、学生生活とも重ねて考える場面が多くありました。今回のお話が、学生の皆さんの一歩につながると嬉しいです。
桝太一さん、貴重な機会をありがとうございました!
(取材・文 京都府立大学 公共政策学部 森川綾子)
(取材 同志社大学 法学部 足立隼太郎
京都府立大学 公共政策学部 遠藤彩花
同志社大学 文化情報学部 斎藤夏帆
京都府立大学 生命環境学部 井手上友香
京都橘大学 経営学部 片山治樹
龍谷大学 政策学部 大神芽吹
立命館大学 文学部 福田拓)