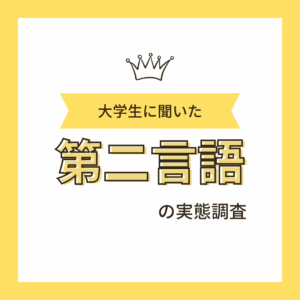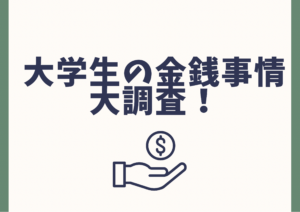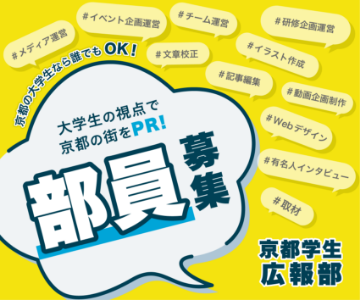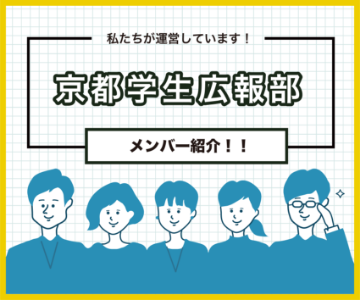【学生がつなぐ!京の社長バトン】福寿園社長・福井正興氏に聞く京都の魅力

こんにちは!
皆さんは普段お茶を飲みますか?お茶は日本人に欠かせないものですよね。
今回から、京都に本社がある企業の社長にお話を伺う“社長インタビュー”企画がスタートします!第一回目として、木津川市に本社を構える福寿園にお伺いしました。福寿園は1790年創業の宇治茶の老舗茶舗であり、みなさんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。9代目社長の福井正興氏に、お茶のことや京都の魅力について語っていただきました。
もくじ
日本の文化を守る福寿園のお茶

―福寿園さんのこだわりについてお聞きしたいです。
お茶に対する向き合い方について、福寿園に代々伝わる「無声呼人(むせいこじん)」という家訓があります。徳のある人のところには呼ばれなくても人が集まるという意味なんです。
お客様に向けて信頼ある本物を届けたい。真面目に良いお茶を作っていれば、売り込まなくてもお客様は手に取ってくださる。信用の蓄積が徳を積むことになるという教えです。
―お客様から手に取ってもらえるお茶を作りたいということで、現在取り組まれていることはありますか?
僕は自分自身のことを間違いなく「世界一のお茶好き」だと思っています。だからお茶のことを皆さんにも深く知ってもらいたい。例えば、お茶がどのように作られているのか、どのような歴史があるのかなど、ペットボトルからでも良いので、お茶について興味を持ってもらいたいと思っています。そのために、お茶への理解が深まる施設などを増やしています。ペットボトルでお茶を飲むことが主流の時代になり、お茶の葉を見たことがない人もたくさんおられます。ですので、急須からお茶を淹れて飲むといった様々な体験にも力を入れています。
―近年、外国人観光客の抹茶の人気が高まっていますが、そのことについてはどのように考えていますか?
日本の国産茶葉は世界的に見て生産量が少ないのが現状です。そのうえ農家さんも激減して茶葉の生産量が減っているので、海外の方がたくさんお茶を買ってくれることを喜んでいられる状態ではないです。とはいえ、日本茶の素晴らしさを伝えていくことは我々の目指しているところでもあります。日本は国土が限られているので、頑張っても生産量には限界がある。海外で生産された日本式緑茶のようなものが増えると、さらに日本の生産量が減少してしまうと考えています。そのような悪循環が起きて日本のお茶がなくなってしまうことが一番危惧していることです。
お茶は日本文化の中心に存在する大切なものなので、これをどのように守っていくかが課題だと感じています。海外で生産していくのも良いですが、同時に日本の文化も守らなければならないという使命感を持っています。
家業を継ぐつもりがなかった学生時代

―同志社大学の商学部をご卒業されたとのことですが、学生時代は茶道部に所属されていたそうですね。
実は茶道部に入ったのはたまたまで、特に周りの人から言われたわけではないんです。大学の入学式で偶然中学時代の同級生に会って、その時に誘われて田辺キャンパスの部室を覗きにいったことがきっかけですね。
茶道部の活動でお茶の作法が身につき、自然と興味を持つようになりました。
―家業を継ぐことになったのは、どのような経緯なのでしょうか?下積み時代などはあったのでしょうか?
大学生の頃は、家業を継ぐという意識は全くなくて、食品関係の仕事をしたいと漠然と思って普通に就職活動をしていました。ただ、幼い頃から家の庭に茶の木があり身近な存在ではありましたが、お茶の事を何も知らないと気づき、卒業後すぐに静岡で二年間お茶のことを学びました。
お茶のことを学んでいる時に大変だと思ったことはなかったです。家業を継ぐことは壮絶なイメージがあるかもしれませんが、プレッシャーを感じることはなかったです。なるべくしてなったのかもしれませんね。(笑)
―学生時代にもっとしておけばよかったと思うことがあればお伺いしたいです。
もっと勉強しておけばよかったというわけではないのですが、色々な方にもっと話を聞いておけばよかったと思っています。当時は4年で卒業できればいいやと考えていました。今は講演やイベントなどに積極的に足を運ぶようにしていますが、大学生の時からそのような経験を一回でも多くしておけば良かったですね。
新しいものに触れる時間を大事に

―福井社長ご自身のことについてお聞きしたいです。
お仕事以外ではどんなご趣味があるんでしょうか?
やっぱりお茶が好きですね。お茶のことを勉強していると楽しいし、趣味も仕事も一体化していると思います。お茶に触れていると癒されます。
あとは趣味とは言えないけど、新しいものを見に行ったり、食べに行ったりもしますね。世界中どこでも見ておきたい!という気持ちがあるので、新しいイベントがあったら自分の目で見に行きますし、それが自分のためになると思っています。
例えば最近だと、お誘いいただいて南座で歌舞伎「刀剣乱舞」を見ましたよ。原作の刀剣乱舞については全く知らなかったので事前にアニメを見てから行きました。ちょうどその鑑賞した数日後、剣の特別展の案内が目に入り、刀剣乱舞で見た剣が紹介されていることに気付きました。刀剣乱舞を見ていなかったらきっと見逃していたでしょうね。
―ご自身の座右の銘は?
「果敢に挑む」という言葉です。この会社は二百年以上の歴史がありますが、過去にとらわれすぎたら前に進めない。社会がどうなろうが、一歩踏み出していくことを一番に、前を向いてやっていく。それしかないです。
近くを通るとお参りしたくなる大切な場所

―京都についてお聞きしたいのですが、京都の街が持つ一番の魅力は何だとお考えですか?
「探し物が見つかる街」だと思います。ものだけでなく、心や人など街を歩いているだけで探し物が見つかる、世界でも稀な街だと思います。伝統だけでなく、新しいものがある。京都にいるだけで、足りないものを埋めてくれるように感じるんです。
―京都でお気に入りの場所はありますか?
お気に入りの場所!えっ!(考え込む社長)
そう言われるとここ山城地域が外せないけど(笑)。
私の愛する山城もいいけど、一つ挙げるとしたら八坂神社さんですね。理由はいくつかあるのですが、大学の茶道部に入部するきっかけの花見歓迎会が行われたのが、八坂神社近くの円山公園だったことや、僕の息子が祇園祭長刀鉾のお稚児さんをさせていただいたことがきっかけで深く知ることになりました。タクシーに乗っていても手をあわせますし、近くに来たら「拝んでいこう」という気持ちになりますね。
―もし今、京都の学生に戻れたらやりたいことはありますか?
京都の学生に戻れたら!どうしよう(笑)。
ただ、学生の時に会社を起こしてみたかったですね。当時はそんなことは思いもつかなかったけど。
―それはどんな会社でしょうか?
昔の夢はおもちゃ屋さんでした。子どもの頃は自慢げにおもちゃを紹介するような時代だったので。会社を一からつくるならお茶以外の違うことをやってみたいですね。未来の子どもたちがワクワクする夢が描ける事業がやりたい。今はお茶から離れられないし、前を向いて果敢に挑むと決めたので、やっぱりお茶のことが頭から離れないです。
この街、地域、会社、歴史があって今の自分がいて、こうやって話ができているので、それに感謝してこの街を守りたいと思っています。
おいしいだけではなく価値を高めたい

―今、福寿園さんが注力している商品やこれから取り組みたいことはありますか?
最近は高級シリーズを見直したり、「ボトルドティー」などの高付加価値のある商品を作ったりしています。「ボドルドティー」という商品は、京都府産の茶葉が持つ旨味を最大限に引き出すため、低温でじっくり抽出しボトルに詰めたお茶です。
お茶農家さんなど何重もの手が加わってできているもので、我々はそれに見合う価値を付けることに力を入れています。
国内の生産量や農家さんの問題もあって、私たちが農業を始めても足りない。世界中の人に日本茶を渡そうと思っても1グラムも渡せない。そんな希少なものだからこそ、最大限の価値を付けたいです。今ペットボトルのお茶は水よりも安く売られていることもありますが、おいしいだけではなく、そこに意味ある価値を付けていくことが大切だと考えています。
また、「食べるお茶」として、飲むだけでなく食材としてのお茶も提案しています。お茶はスイーツに使われることが多いですが、お茶を使用したフランス料理など、料理食材としてお茶を活用する取り組みを行っています。
これからもお茶を使った食品開発に力を入れ続けたいと考えています。
さらに、「アートスペース福寿園」というお茶に関するアート作品のギャラリーも始めました。アートとお茶は相性が良い。お茶は喉を潤すだけでなく、心身ともに潤すものだと位置付けています。アートを愛でて癒されるということと共通点を見出せると思って取り組んでいます。
話したいことはまだまだ五時間ぐらいありますね(笑)。
おわりに

社長インタビューということで、始まる前は緊張しましたが、明るく気さくに話して下さりました。質問に対して、常に未来を見据えたことを話されている姿が印象的でした。
「世界一お茶好き」と仰っていたように社長の持ち物も緑色に揃えられていて、お茶好きを感じました。
取材後には「福寿園山城館」を見学し、お茶が商品として販売されるまでの過程を学びました。日本茶の歴史と素晴らしさを改めて感じた取材でした。
福井社長、インタビューのお時間をいただきありがとうございました。
次回の社長インタビューもお楽しみに!
(取材・文 同志社大学 文学部 井本真悠子)
(取材 京都府立大学 公共政策学部 森川綾子)
(取材 京都産業大学 文学部 水取咲綾)
(写真 同志社大学 法学部 足立隼太郎)