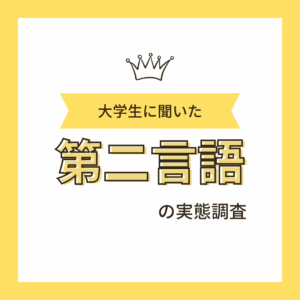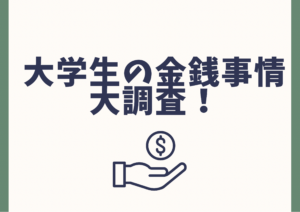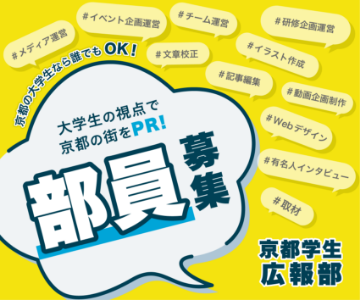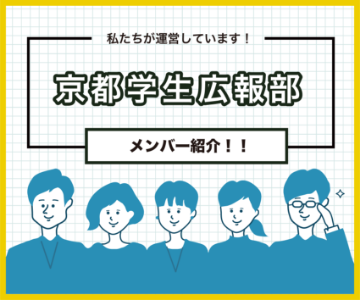「蜷川実花展 with EiM:彼岸の光、此岸の影」をレポート!

2025年1月11日から3月30日にわたって京都市京セラ美術館にて開催されている「蜷川実花展 with EiM : 彼岸の光、此岸の影」を見に行き、京都市京セラ美術館事業企画推進室ゼネラルマネージャーである高橋信也さんにお話を伺いました!
今回の展覧会のタイトルに入っている「此岸」とは仏教用語で「現世」、「彼岸」とは「死後の世界」という意味を持ちます。この言葉と関係する展示に込められたストーリーについてもお話を聞けたのでぜひ読んでみてください。
もくじ
絵巻のように繋がった世界
まず、高橋さんにお聞きした展示の意味とともにレポートしていきます!実際に行かれた方は自分の感じたことと照らし合わせてみてください!
暗い廊下を抜けると、「Silent Fire Distant Echo(直訳:静かな炎、遠くのこだま)」という赤い言葉とともに映像が映し出された水槽が現れます。地面に置かれた四角い水槽には花々や金魚、そして四条河原町や渋谷といった都市が映し出されています。

見覚えのある京都の風景に気付いた方も多いのではないでしょうか。この部分の展示で、自分が知っている景色を探してみるのも楽しいかもしれませんね!
次に進むと左右が彼岸花で埋め尽くされた道になっており、一気に別の世界へ向かっていくような不気味な雰囲気が漂っています。

この道が三途の川のように、私たちの生きる此岸から次の彼岸への道になっているのです。
次の部屋では、前後二枚のスクリーンに様々な花の映像が映し出されています。
表裏から映し出される映像が重なり合うことで両方の映像にピントを合わせられず、自分のいる場所が分からなくなるような不思議な感覚に陥ります。

次の部屋へ進むと小さな額縁に入った絵が飾られています。額縁にはパーツが無数に付けられており、その細かさに思わず見とれてしまいます。

蜷川さんご本人がこの部屋にテーブルを持ってきて、ピンセットを使って作業をされたこともあるそうです。

額縁の中の絵には、泣き叫んでいる子猫や街を歩いている女の人の脚だけがあったり、真っ赤な口紅を塗った女性の口元が描かれたりしています。
「彼岸へ着き、ようやく冥界に行ってこれから落ち着いて眠れるかな、というときに、どうしても嫌なイメージが広がってきて眠れなかったり気持ちを持っていかれたりする。死んで安らぎたいのに、安らげない。」それがあの部屋のイメージだそうです。
このようなことは普段でもあるかもしれません。例えば、眠ろうとするとふと何か嫌な出来事が思い浮かんで、そのことばかり考えるようになってしまって眠れなくなるというようなことです。
次の部屋に行くとL字のガラス板が並べられています。このガラス板は色々な花が映されていて、照明が当たると床に映し出されるようになっていてとても綺麗でした。

画像そのものではなくて、光に漂う感覚がどうも生きている感じがしません。また、L字型のもう片方のガラス板は鏡にもなっており、前に立つと向こう側が見えるのにも関わらず自分の姿も映ります。
つまり、そこで「自分は透明なんだ」と自分が霊魂で実体がないことを感じるのです。そこをうろうろするのが、この部屋だそうです。
その向こうではクリスタルガーランドが作り出すクリスタルの森のようなものが広がっています。蜷川さん自身が1年半ほどかけて作ったもので、既製品のガラス球を繋げているだけでなく、ご自身で作られたパーツも織り交ぜられていました。

1500本ものクリスタルガーランドを天井から吊るす作業は2週間ほどかかったそうです。そのクリスタルガーランドの真ん中を「霊魂である私たち」が歩いていく。誰も何も言わずに列を作ってその間を通っていく様子は、これまでの展示ストーリーを考えると少し不気味な光景です。
その先にはお花の森が待っています。

すべて造花なのですが、不思議なのが春夏秋冬の花が全部同じ空間にあることです。そして蜷川さん自身は本来写真を見せることで表現をしているはずですが、あの空間には1枚も写真がないのです。
ただし、どの角度から切り取ってもすべて蜷川実花さんの作品になっていました。最近の言葉で言うとイマ―シブで、没入感がありました。
黄泉の奥底のようでもあり、天上の世界のようでもある空間の体験は「彼岸の夢」のようです。
造花の森を進んでいくと、次の部屋では壁いっぱいに映像が映し出されています。

映像が上下に動いていて、天井と床は鏡になっているので、上を見たり下を見たりするとそもそも登っているのか落ちているのかよくわからなくなってきます。
ここは、自分の心の中を此岸から冥界のほうに戻り、行き着いた場所が転生する部屋であると考えられています。そのあとまた奈落に落ちていくのです。
続く廊下を通ると、スクリーンに映像が流れています。座布団が置いてあるので皆座ってじっくりそれを見ることになります。

東本願寺や西本願寺には巨大な伽藍(がらん)がありますが、それは仏様に許しを請いたい生者が疚(やま)しさと引き換えに作ったものです。この展示部屋は、その伽藍のイメージがあるといいます。浄化・成仏する部屋とのことで、光が多く、白い印象を受ける映像に癒された方も多いのではないでしょうか。
「造花の森を抜けたら冥界の奈落に落ちて、転生した自分が浄化されて現世に戻る。」
戻ってすぐに現実というわけにもいかず、展示が終わって戻ったところの廊下のガラスの花の写真が私たちを余韻とともに現実へと紡ぎ直します。

以上、展示のストーリーはいかがでしたでしょうか。実際に見て感じたこととはまた違っていたかもしれません。このほかにも一つ一つの展示に細かな意味が込められていました。
一つ一つの展示に込められた意味を知った上で写真を見返してみると新しい何かに気付くかもしれません。
京都ならではの表現

京都にはたくさんのお寺・神社があり、数多くの宗教が流布していました。
京都で生まれた歌舞伎や能は生死を題材としたものが多く、此岸から彼岸への境が描かれていました。
松原通にある「六道の辻」は「冥土へのわかれ道」として古くから知られており、死後に輪廻転生する六つの道の分岐点として此岸と彼岸の境(接点)となっています。
「六道の辻を上がっていき、さらに東山を上がりきったところで清水寺のお庭に出ます。
それまで死者の群れだったのが、清水の観光客の群れに突入します。それが素晴らしい転換で、死者の森から生者の森へ移るという感じがするのです。」
そのような話を高橋さんは蜷川さんとされたそうです。
また、堀川には戻橋という橋がかけられており、死者が「戻る」橋と言われています。
その他にも京都には多くのお寺があり、死者と生きている人間が実は隣接して暮らしている町だと分かります。蜷川さんはこの展示で此岸と彼岸を象徴的に表現していますが、実は京都中に広がっているのです。
面白がって見ることが大事!

京都市京セラ美術館事業企画推進室ゼネラルマネージャーである高橋信也さんに展覧会のストーリーや京都とのつながりについてお聞きしましたが、ここからは高橋さんの思いや展示の裏側をお聞きしたいと思います!
―まず、この展覧会は来場者の方にどのように楽しんでもらいたいと考えていますか。
先ほど作り手側の様々なコンテクスト(今回の展示のストーリー、文脈)をお話ししましたが、どのように捉えていただいてもいいと思っています。
ただ、蜷川さんは見る人の感情を捕まえながら一部屋一部屋をつなごうとしているので、その点に関してはある連続性を持って見てほしいと思います。
―では、伝えたい意図がはっきりと伝わっていなくても大丈夫ということですか?
今は京都になぞらえて話をしましたが、必ずしも京都でなくてもそういうことってありますよね。相当多義的なものなので、それぞれ見た人が自由に解釈すればよいのではないかと思いますね。
―作品を見るときに写真をたくさん撮る人が多いと思うのですが、例えば写真を撮ることが目的になってしまっているとすれば、展示する側から見るとどのように考えますか。
そればっかりになると確かに困るけれど、蜷川さん自身は写真をたくさん撮るということに必ずしも否定的でないと思います。
昔は写真というと重い機器を持って三脚を立てて撮るものだったのですが、蜷川さんがデビューした90年代後半はガーリーフォトといって女の子たちが身近なものでおしゃべりするみたいに撮る、というものが流行りました。蜷川さんの作品はガーリーフォトの代表の一つだったので、女の子たちは写真を撮るという行為の中に楽しみを見つけたのかなと思います。
―逆に写真を撮られることを前提として展示をするということもあるのでしょうか。
作家によってそういう意図をする人がいたら、あるのかもしれないですが、美術館としてそれが前提になるということはないですね。
―そうなのですね。
ただ、一方的に見せるだけというのは現代美術ではなかなか無くて、読み取ってもらってリレーションして(関わりあって)もらうということを大事にしています。
―展示についてお聞きします。準備に時間がかかったものはどの展示でしょうか。
やっぱり《深淵に宿る、彼岸の夢|Dreams of the Beyond in the Abyss》のインスタレーション(観るだけでなく展示空間そのものを作品とするアート)は10人ほどが10日くらいかけて製作したので大変だったと思います。生け花を生けるみたいにして、照明を当てながらするのですが、微調整にすごく時間がかかるんですよね。
モノを作るとき、だいたい8割くらいまではすぐに行けるのですが、残りの2割を作るのに最初の8割と同じ、もしくはそれ以上の時間がかかります。

―それを知ってから見るのもまた面白いですね。
そうですね。全然違うと思いますよ。
準備期間は合わせると20日ほどかかりました。絵を飾るだけの展示なら大体10日程度なので大変でしたね。
―製作者の蜷川さんと他のプロデューサーの方たちがそれぞれどのように関わり合っているのですか。
展覧会ごとで変わるのですが、蜷川さんの展示デザインは美術館のスタッフがやっています。考え方をブレストしていく中で、蜷川さんがそれに合わせてこんな感じかなと絵を描いて調整していきました。
映像の中身などに関しては蜷川さんに任せていました。蜷川さんは、過去に彼岸花だけの展示やクリスタルガーランドの展示を小規模でやっていて、今回ここに集結しているんです。パーツなどをいろいろ使って相応化させていましたね。
―この展示で使われていた花の映像などは今回のために京都で撮影されているものが多いのでしょうか?
多いわけではないですが、蜷川さんが撮った京都の桜の写真が使われているところもあります。毎年京都の原谷に桜を撮りに来られているみたいです。
最初の水槽の中の映像にも大鳥居や京都市京セラ美術館、渋谷、河原町の風景が出てきましたね。僕は一緒に街を歩いたのですが、彼女は何気ないものも写真に写すんです。今回の展示にもその写真が紛れていると思います。
そして主催者側として驚いたことは、カメラを持ったたくさんの若い女性が蜷川さんの作品に向かい合うときに非常に真摯な姿勢であったことです。普通の展覧会では見られない光景でした。
―この記事を読む学生にメッセージをお願いします!
この展覧会をどう解釈するか、ということを話しましたが、まずはそれよりも面白がって見ていただくことが1番だと思っています。
本当に面白いと感じたときに、次は何をみたいと思ったり、自分のことをどうしたいと思ったり……。色々と考えることがアートに向かう力になると思うので、ぜひ楽しんで面白がって見ていただくことが1番良いことじゃないかと思います。
さいごに

今回の取材では高橋さんにしか聞けない展覧会開催の裏側や細かいストーリーまで聞くことができました。関西最大規模で行われたこの展覧会ですが、京都で開催された意味がよく分かりました。
実際に展示を見に行かれた方も写真を見返してみると新しい発見があるかもしれませんね。
京都市京セラ美術館事業企画推進室ゼネラルマネージャー・高橋さん、ありがとうございました!
(取材・文:京都府立大学 生命環境学部 井手上友香)
(取材:同志社大学 法学部 足立隼太郎)