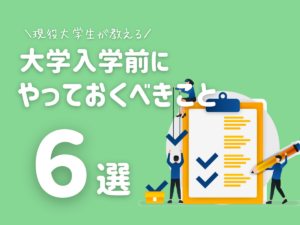久美子と同じ場所で花火を見ていた|『特別編 響け!ユーフォニアム~アンサンブルコンテスト~』石原立也監督取材(後編)

前編に引き続き、最新作『特別編 響け!ユーフォニアム~アンサンブルコンテスト~』劇場上映を記念して、監督を務める石原立也監督のインタビューをお届けします。
後編では『響け!ユーフォニアム』(以下、『ユーフォ』)シリーズのお話からさらに広げ、石原監督ご自身や出身地の京都について、そして「京都アニメーション」(以下、「京アニ」)のものづくりについても伺いました。
前編はこちらから
もくじ
きっかけは、幼いころに描いた「リンゴの絵」
——アニメーションの監督は、どんなお仕事をされるのでしょうか?
たぶん、映画の監督と同じですよ。映画監督さんって、役者さんのお芝居の撮影を見て、「カーット!」とか言ってそのお芝居にオッケーを出したりするじゃないですか。アニメーションの監督や演出がやることも一緒で、現場の作画スタッフが描いたキャラクターのお芝居を見て、「はい、オッケーです」とか、ダメなら「ここのお芝居、もうちょっとこうしましょうよ」という感じでアドバイスするんです。
背景も絵コンテをもとにして作るんですが、監督も背景スタッフと一緒に考えます。「ここは夜なんだけど、ちょっと暗めの夜にしましょう」とか「ちょっと青っぽい感じの夜にしましょう」とか、光の方向を考えたりするのも監督や演出なので、仕事の幅はかなり広いです。
監督や演出の人によっては、自分でちょっと手を入れる人もいらっしゃいます。
——演出と監督の仕事の違いはなんですか?
そうですね……。一般的には、TVシリーズの1本1本を監督のように見る人が「演出」で、直接上がってきた原画を見る仕事をしています。だから、ちょっと肉体労働派なんですよ。
一方、「監督」はもう少し作品全体の流れも見ることが多くなるので、頭で考える仕事が多いですね。どちらも大変なんですが、僕としては最近年齢もあり、体を動かす仕事はちょっとしんどいなって思い始めています。物理的にね。
——では、石原監督自身がアニメ業界を目指したきっかけはなんだったのでしょうか?
「最初はあれかな」と思うのは、幼稚園のときにリンゴの絵を描いて、その絵を親に褒めてもらったんですよ。おぼろげな記憶ですけど、それが絵を描くのが好きになった最初のきっかけのような気がします。
——記憶に残る大きな体験だったんですね。
その後、小学2 年生のときに、いわゆる“戦艦が宇宙を飛ぶ”アニメにハマりまして(笑)。やっぱりね、1970 年代ぐらいに育ったアニメっ子にとって、あれはとても影響が大きかったんですよ。ロボットは出てこないけど、すごくSF感が強い物語だなと思って、ハマったんです。あの作品は今でいうと「オタクっぽい」行動を僕にさせ始めた最初の作品だと思いますね。この頃に漫画家を意識し始めていたかな。

小学校高学年、中学校あたりからは本格的にアニメーターの名前を覚えました。あの頃はアニメブームであると同時に、アニメーターブームでもあった気がします。かなりガツンと来る作品が多くて高校生ぐらいの頃からはもう、「アニメーションの仕事をしたい」という気持ちも具体的になっていたんです。
——そうなんですね。進路選択で迷いはありませんでしたか?
意外となかったですね。他にやりたいことがなかったというのもあるし、あの頃はすでに「大人がアニメを見てもいいよね」という雰囲気になっていたので。むしろ、本格的に迷うのは仕事を始めてからですね。
——仕事を始めてから、ですか?
僕の場合、進路の選択自体は安易だったんですけど、その後は結構苦労したんです。僕が監督をさせてもらえるようになったのは40歳過ぎなので、割と遅めなんですよ。僕の専門学校の同級生だと30代で監督や美術監督になっている人もいましたし、同級生がどんどん重要なポジションに就くことに対して、僕自身の力不足を感じていろいろと悩みました。
だから、この仕事は面白いけど結構しんどいことも多い、ということは若い人たちに知っておいてほしいですね。
——では、どんな経験が今の仕事に活きていると思いますか?
やっぱり絵を描くこと……かな。僕らが育った頃って、パソコンもスマホもなかったので、娯楽といえば僕自身は絵を描くことぐらいしかなかったんです。だから、高校生の頃はラジオを聞きながら夜中の3時ぐらいまで漫画を描いていたけど、好きで描いていたから全然苦ではなかったですね。本当に趣味で描いているだけなんですから。
あと、子どもにしては映画も観ていたような気がするし、それも役に立っているのかな。
——趣味を突き詰めていった、ということですね。
かっこよく言うとね(笑)。
京都は絵になる場所が多い
——石原監督は京都府出身ということですが、「京都の魅力」についてどう思われていますか?
僕の出身は京都府の舞鶴なんですが、京都の街でいちばんの魅力だと思うのは、活気ですね。新京極とかへ出ると、皆さんみたいな若い方がいっぱいいるので、それは魅力のひとつかなと思いますね。やっぱり、若い人が沢山いる街というのは、とてもいいと思いますよ。若い人がいると、若い人向けのお店もいっぱいあるじゃないですか。街自体がなんだか若さに溢れていて、いいなと思ったりします。
あと、宇治とか京都は、絵になる場所が多いと思いましたね。久美子の家の近くの喜撰橋はこぢんまりとしつつも、絵として「綺麗だな」とも思うし。でもちょっぴり残念なのが、宇治の花火大会がなくなっちゃったことですね。
——台風の影響もあって2014 年以降なくなってしまったとか。
結構長く続いていた行事みたいですね。これは自画自賛ですけど、『ユーフォ』の第2期の第1話にある花火大会の様子は、割とリアルに描写していると思っています。
——リアルに再現されているからこそ、実際に見てみたかったという想いが強いです。
そこまで大きな花火大会ではなかったですが、綺麗でしたよ。宇治の花火大会の打ち上げ場所と、久美子たちが花火を見ていた喜撰橋は結構離れているんですよ。でもあそこから見ると、ちょうど打ち上がった花火が宇治川にも映るのが綺麗で……。
今から30年くらい前だと、あの辺にはあまり人がいなかったんですよ。最近になって、喜撰橋の辺りに見物人がだんだん増えてきたんです。なんかそんな思い出があったりしますね。
——あの花火のシーンは石原監督の経験も入っているんですね。
はい。久美子たちがいた喜撰橋の袂はすごく狭い場所なんですが、僕は実際にあそこに座って見ていました。ただ、浴衣につっかけで、というとちょっと危ないかもしれないですけど(笑)。

(久美子と麗奈が橋の袂から花火を見上げているシーン)
——確かに危険かもしれないですね(笑)。『ユーフォ』シリーズを含め、京アニ作品は視聴者を感動させることにとても力が入っていると思います。感動シーンを作る際、どんなことを考えながら制作しているのでしょうか?
感動シーンに関しては、僕自身はなんとなく、作り手からお客さんに「ここが感動シーンですよ」とか、「ここで泣いてください」と要求するようなフィルムを作るのは若干おこがましいような気がしています。だから、「こうだったら僕は感動するな」と自分を基準にした作り方でしか作れないかな。
——ちなみに、感動シーンを描きながら泣くことはあるんですか?
ありますよ、いくらでも。テレビシリーズの絵コンテを描いているのは監督じゃない場合もあるんですけど、例えば『久美子3年生編』でも、とてもいい絵コンテが上がってきて、僕も読んでいて泣いちゃったことがあって……。
——感情移入しながら制作されているんですね。
でも難しいのは、泣ける基準が人や育った環境、見てきたものによって異なる場合がある、ということですね。「自分は泣けるけど、他の人は泣いてくれるかな?」と思ったりするけど、そこはもう、自分の感覚を信じるしかないんで。泣けるかどうかがお話の全てでもないような気もするし。
でも最近感じるのは、やっぱり若い頃より年を取ってからの方が泣けますよ。本当に。
——そうなんですか?
原作小説でも、北宇治高校吹奏楽部副顧問の美知恵先生のセリフで「若い人が頑張っているのを見るだけで泣けるんだ」って言葉があるんです。僕が若い頃にそのセリフを聞いてもわからなかったかもしれないんですが、この歳になってくると、とてもよくわかるなって思いますね。本当に、若い人が頑張っているのを見るだけで泣けるんです。
同じ場所にいるからこそ、次の世代に技術を継承できる
——京アニ作品を「観たい!」と思うファンが世界中にいますが、石原監督が考える“京アニらしさ”とはなんですか?
“愚直さ”かなって思います。手前味噌かもしれないですが、本当に真面目なんですよ。もちろん、他の会社もそうなんでしょうけど、とても一生懸命やるので、そこが“京アニらしさ”だと思っていますね。
——そういった“愚直さ”が視聴者にも響いているんですね。
だといいなと思いますね。最初は“京アニらしさ”というものはなかったと思います。2003年の『フルメタル・パニック?ふもっふ』から2012年ごろまでの作品は元請けですが、それより前は、セル(画)に色を塗る仕上げの仕事をやっていたんですね。その頃から、「京アニさんのセルの塗りはとても綺麗ですね」って評判が良かったんです。だから昔から真面目な印象はありました。
——確かにアニメーションを見ていると、京アニは作品を通して画作りがとても綺麗というのが魅力のひとつだと感じます。そのクオリティを維持するために大切にされていることはありますか?
僕より若い人たちを見ていて感じるのは、やっぱり“技術の継承”が大事なんでしょうね。京都アニメーションとしてひとつになって仕事をする良い部分だと思うんですけど、直接技術を教えられるんです。それは単なるテクニックだけじゃなくて、ものを作るときの考え方とかも教えられる。
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の監督などを担当している石立(太一)さんとか、『アンコン編』副監督の小川(太一)さんとか、僕よりもうちょっと若い世代がいるんですけど、彼らが一生懸命に質の継承をすることで、次の世代に繋がっているのではないかと思いますね。

——今後のアニメ業界はどうなっていくと思われますか?
そうですね……。最近って極端な話、AIで絵を描いたりするじゃないですか。ああいうものは進化すると、ひょっとしたらいろいろなことがクリアできてしまうかもしれないですよね。でも、これが良いか悪いかの判断は難しいですけど、テクノロジーの進化によって、逆に“描けないもの”が多くなるんじゃないかと思います。
例えば、『ユーフォ』シリーズでは電車がよく出てきますけど、ああいうのって、昔は手で描いていたんですよ。でも、今だとCGでやっているんですね。CGでできるから、まあいいかとも思うんですが、そういったものを描かなくなると、今度は“描けなく”なってくる。
僕としては、やっぱり描けるものが減っていくというのは若干不安がありますね。数十年先には紙に作画できる人もいなくなるんじゃないかと思ったりもします。
——難しい問題ですね。これからアニメ業界に入りたい若者やクリエイターに期待していることはありますか?
本物とか実物とか、リアルなものをしっかり見る経験は大事だと思います。ネットやスマホで簡単に調べることができても、それだけが全てじゃない。経験が生み出す“頭の回転の速さ”は重要なんじゃないかと思っています。
——では最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。
世界や日本の情勢もいろいろ大変です。でも、やっぱり若い人には頑張ってほしいんですよ。もちろん僕たちも若い世代に人任せにするつもりはないので、一緒に頑張っていきましょう。
——ありがとうございました!
最後に

石原監督のさまざまな経験が今のお仕事に活きていて、さらに次の世代に繋がっていくんですね。
世界中のアニメファンが「京アニ」に夢中になる理由も、垣間見えたのではないでしょうか?
改めまして、石原監督、貴重なお話をありがとうございました!
前回、『響け!ユーフォニアム』の作者、武田綾乃さんにインタビューした記事はこちら。
(取材・執筆:同志社大学 グローバル地域文化学部 西村彩恵)
(取材:立命館大学 文学部 吉田玲音)
(取材・執筆協力:同志社大学 文学部 井本真悠子)
(撮影・執筆協力:立命館大学 文学部 小関萌嘉)