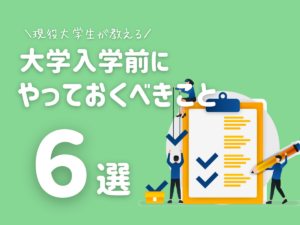音楽と教師の道を歩む-原田博行さんが語る「二足のわらじ」(後編)

シンガーフォークソングライター&ティーチャー。さらにサウンドロゴ・クリエイター(※サウンドロゴ…企業名や商品などをアピールするための、短い曲)というマルチな肩書をお持ちの原田博行さん。
前編はこちらから
後編は、教師になるまでの経緯や、最近の活動に迫ります。
もくじ
大学卒業後に知った制度で、講師になった
――バンドでの挫折や洗礼は原田さんにとって大きな出来事だったと思います。大学卒業後はどのように過ごしていましたか?
大学を卒業して2年目の時には「プロで音楽をやりたい」のかわからなくなっていました。そんなころ、同志社大学が「科目等履修生制度」というものを始めたことを知りました。卒業生を対象に免許・資格取得するために必要な科目を履修できる制度です。
僕は在学中に教職課程を履修していたのですが、試験日がライブと重なって……。単位を取り切れずに卒業したんです。一方で、僕は中学でも高校でも周囲から「先生に向いている」とずっと言われてきました。
卒業から2年がたち、音楽仲間みんなが東京に行くタイミングにこの制度を知って、教員免許だけ取ろうかなと思い、履修をはじめました。
同志社大学卒業生、大学院修了生を対象とした「科目等履修生制度」の案内はこちら
https://license.doshisha.ac.jp/non_degree/non_degree.html
――卒業後に学びなおしてみて、いかがでしたか?
同志社高校で行った教育実習がとても面白かったんですよ。僕は「生徒たちがこれまで見たことがない授業をしよう」と思って授業をするので、生徒たちも「担当は原田が良いわ!」と思ってくれたようです。
すると、3月ごろに同志社高校から「講師をやらないか」という電話がかかってきたんです。この時も、ソロで弾き語りを始めたり、新しくバンドを組んだりと、結局は音楽をやめずに続けていたので、「良いですけど、僕はすぐに音楽で東京に行きますよ」と言いました。
――それでも講師をすることにしたんですね。講師の1年目はどのように過ごしましたか?
まずは1年間やってみようという思いで、1学年9クラスのうち4クラスを担当させていただきました。担当したのは、教育実習で出会った学年の生徒たちでした。その中には、後に脚本家になった三谷昌登がいて、三谷とお芝居やラジオ番組を一緒に作る関係になりました。
講師生活1年目で、「こんなに才能がある面白い生徒たちと出会えるなら、出来るだけ講師を続けたいな」と思ってから今に至り、気が付けば27年が経っていました。
――音楽を続けながら、社会人の4年目で講師になられたということですよね。先生を始めて感じたことはありますか?
高校の授業を初めて行ったときに感じたのは、どの教室に行っても40人が座って自分の話を聞いてくれるのは幸せだ、ということですね。ライブで40人のお客さんを集めるのは大変なんですよ。加えて、ライブと授業は似ているところがあります。ライブハウスも40人くらいのサイズなので、40人の空間を掌るという意味では授業運営と近いんですよね。

僕が担当するのはキリスト教の授業なのですが、学校からは、“命”というテーマで自由に授業を作っていいと言われています。このテーマだと「どういう風に生きていくべきか」とか「生きていくうえで、何が大事か」ということを伝えることが可能です。授業では「キリスト教的な価値観」をベースに伝えることになるのですが、音楽を通して伝えたいことと親和性の高い内容を授業でも伝えられると感じました。
伝える内容に関しては、牧師の父の影響をかなり受けています。「生きていくために必要なことは何かを伝えたい、それはキリスト教なんだ」と信じている人の家庭で育ちました。だから僕も、仕事にミッションやメッセージは必須だと思っています。その生き方を音楽をとおして受け取ったんです。
だからこそ、今は「どんな音楽をするか」よりも、「何かのために歌う、音楽で何かを伝える」ことを大切に考えています。教職免許の試験よりライブを選んだ僕の天職が教師になるなんて皮肉な話ですね。
二足のわらじは、希少価値がある?
――だから現在の肩書は“シンガーフォークソングライター&ティーチャー”なんですね。
教師を初めて10年目くらいに、名刺に“シンガーフォークソングライター&ティーチャー”と初めて書きました。実はコンプレックスを名刺に書いたんですよ。「 &ティーチャーってダサくない?」「“ロック”じゃなくて“フォーク”ってダサくない?」というのが自分の中にありました。でもこの肩書で発信するにつれて、これは希少価値があるんじゃないか、こういう風に生きていけるのっていいなと、自分の中で変化していくんです。
教師の1年目には「100パーセント音楽になるために、仕方なくやっている授業やで」って思っていました。10年目くらいになると、冗談で「原田君、いつ東京に行くの」と周囲の先生に言われることもありました。ただ、この頃に結婚したこともあり、「京都で生きていく」という思いが強くなりました。
また、時代も変わりました。インディーズというスタイルが生まれ、WEBで誰でも発信できるようになったことで、「ミュージシャンは東京に行って、メジャーデビューしないといけない」というかつての雰囲気は無くなりました。
周りに支えられながら、ライブやラジオ番組をプロデュース
――教師としても、ミュージシャンとしても経験を積み重ねていく中で、音楽活動に変化はありましたか?
30代に入ってからは年間50本のライブを行い、新曲は30曲作るなど精力的に活動を続けました。その甲斐もあってかインディーズデビューが決まり、嬉しい反面、もしかすると自分は“お山の大将”になっているじゃないかと不安になりました。
そこで先輩のドラマーにお願いして一緒に音楽活動したりアドバイスをもらったりしたところ、先輩から「何本もライブして年間に延べ800人のお客様が集まるライブではなく、年に1回、800人集まるライブを開催してみたら?」って言われたんです。
その言葉で、小さなライブを繰り返すこれまでのスタイルを見直し、年に1回「ハラダイス・ライブ」を開催すると決めました。
先輩が僕に「向いている」と言ってくれた円山公園音楽堂でのライブを実現するために、この時初めてスポンサーを集めるための営業をしました。「自分には何が出来るか」を考えた結果、「御社をPRする曲を1曲作るので、人数分のチケットを買ってください」という僕の強みを生かした営業スタイルが生まれ、京都中の会社を回りました。
1回目の「ハラダイス・ライブ」が終わってから、ライブと連動させたラジオを企画し、番組をスタートさせました。そのラジオは終了しましたが、その頃フリーマガジン『ハンケイ500メートル』の円城新子編集長と出会ったんです。
『ハンケイ500メートル』円城新子編集長との出会い
――円城さんは、現在放送中のラジオ番組で共演されている方ですよね。円城さんと出会った経緯について教えてください。
僕が営業に行っていたスイーツ店の店主が、レシピ本を円城さんが代表取締役を務める出版社から出版されたんです。その出版記念パーティーで円城編集長と出会いました。
僕はこの時、東北に震災の復興支援としてサウンドロゴをつくりにいっていた活動を、本にしようと思っていたんです。過去に出版社の知り合いに相談したら、「まずはどこかで連載を持ったほうが良い」と言われて、東北の「河北新報」で連載しました。それから連載が終わり、そろそろ本にしたいなという時に出会ったのが円城さんだったんです。
書籍化について円城さんに相談すると「サウンドロゴを復興支援でつくった話の本って、売名行為に見えてしまう危険性がありますよね。むしろ、サウンドロゴをつくって自分の音楽活動を続けている唯一無二のミュージシャンとしての原田さんの方が面白いですよね」と言われました。それで、自分の音楽人生をテーマにした本を出版することになりました。
――なるほど、ではラジオ番組の企画はどちらの提案でしたか?
それは円城さんです。僕の本の出発準備と同時期に、「今度はラジオ番組を一緒にやってもらえませんか」と依頼がありました。「すべてのスポンサーをサウンドロゴだけで紹介する番組にしたいんですよね」って。
7月に出会って、10月から番組が開始しました。番組では、「今日のハンケイ500メートル」という、毎回1つのバス停を取り上げて、トーク内容から場所をリスナーに推測してもらうコーナーがあります。これは、番組の企画段階からありました。

――番組では、フリーマガジンやサウンドロゴの取材の裏話もされていますよね。
円城さんがフリーマガジンの取材をした方たちに向けて、僕がサウンドロゴを作ることも多いのですが、フリーマガジンを作る時と、歌詞を作る時の取材では、聞くことが微妙に違います。そういう面ではお互い面白いですね。聞き出し方や、相手の話から選び出す言葉が、少しずつ違う。目的が違うのですから当たり前ですが、取材対象の本質を拾い上げるという点では共通するものがあって、円城さんの取材やその裏話は、僕にとってもすごく勉強になります。
活動を続ける中で感じること・中高生に伝えたいこと

――活動を続ける中で、京都の街についてどう捉えていますか?
僕の教え子は、27年間で1万人くらいいます。最初の教え子たちは40代になっていて、子どもが高校に入学したり、自分のスポンサーになってくれていたり。仕事に行った先で「息子がお世話になっていました」と声をかけられることもあります。京都は1万人の教え子がいて、ラジオの発信もしている場所です。自分のベースになっている街で、ローカルタレントとして幸せな状態です。
京都に限らず、復興支援に行って地元の方と繋がったことで、東北も地元みたいになりました。京都を選んで京都で活動しているというよりは、ライブをしたりサウンドロゴをつくったり、活動の中で自分のシーンを各地に作れるという感覚があります。
――最後に、中高生にメッセージをお願いします。
人生をかけて取り組むことに、明日出会うかもしれないし、ずっと出会わないかもしれない。
そこに早いとか遅いとかはなくて。ただ、出会っているのに気づかないふりをすることはあると思います。なので、「自分のアンテナをたたむな、広げていけ」と言いたいですね。かっこいいなとか、やりたいなと思うことは、あなただけが感じる感覚なので、それを捕まえる勇気を持っておいてほしいです。
最後に
今回は、高校時代の恩師の原田さんにインタビューを行いました。自分から行動を起こすことで、新たな出会いや進むべき道が見えてくるということが伝わってきました。また、「科目等履修生制度」を今回の取材で初めて知りました。大学を卒業してからでも、学びなおすには遅くないということを感じられる取材になりました。
(取材・文:同志社大学・法学部 梅垣里樹人)
(撮影:龍谷大学・政策学部 梅垣舞央香)
(写真提供:原田博行様)