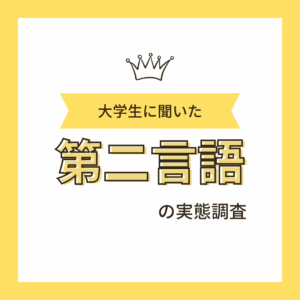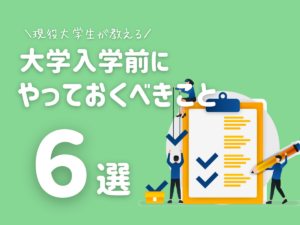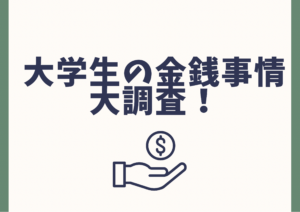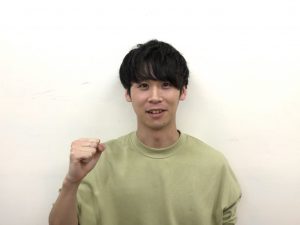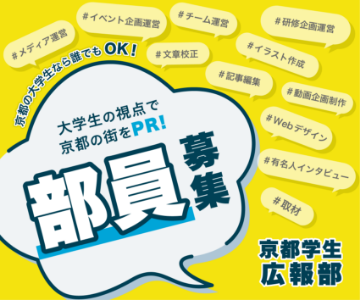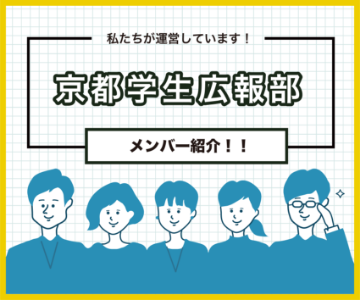文芸評論家・三宅香帆さん直伝!“伝わる言葉”の選び方

いま各メディアで注目を集める文芸評論家・三宅香帆さん。代表作『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が新書大賞2025を受賞し、30万部を突破するベストセラーになるなど、話題となっている方です。
7月16日、京都学生広報部ではそんな三宅さんを講師にお迎えし、文章講座を実施しました。
当日は広報部員と一般参加者を合わせて約40名が参加し、予定時間をオーバーするほど熱気あふれる時間に。言語化の技術やいま必要な言語化について、存分に味わえる講座となりました!
もくじ
ありきたりな表現から抜け出すコツ

今回の講座では、“伝わる文章の書き方”や“自分の好き”を言語化するコツについてレクチャーしていただきました。
言語化の前提として、先生からは「言葉を使う限り、大切なことは全て同じ」とのお話がありました。
その中で特に印象的だったのが、“クリシェ”を避けることの重要性です。
クリシェとは、ありきたりでよく使われる“それっぽい表現”のこと。必ずしも悪いものではありませんが、自分の中でオリジナルな言語化の力を鍛えたいなら、なるべく避けたほうが良いそうです。特に、感想を書くときにありがちな三大クリシェは「考えさせられた」「泣けた」「やばい」。
筆者自身も、「やばい」などの汎用性の高い言葉を使いがちなので、こうした表現に頼らず、自分なりの言葉で感情や気づきを表すことが大切だと学ぶことができました。
先生への質問コーナー
講座の最後には質問タイムが設けられ、多くの参加者が先生に質問をしていました。いくつかの質問を抜粋してご紹介します!
Q.先生はタイトルなどにキャッチーな言葉をよく使われている印象があります。タイトルをつけるときには具体例から入るのか、それとも短い文章で自分を表現する独自のアプローチがあるのでしょうか?
A. 私は、タイトルをつけるときは具体例から入ることが多いですね。抽象的な言葉から始めようとすると、うまくタイトルが決まらないことが多いんです。
普段から、誰かが言っていた細かな言葉を集めたり、「最近こういう言葉、流行っているよな」と感じるようなフレーズをメモしたりするのが好きで、そういう素材からタイトルを作ることが多いですね。
よく「キャッチー」と言われるのですが、実は私はタイトルを短くまとめるのが苦手で。いつも頑張って削って短くしている、という感じなのです。
Q. 書いている途中で、「これ、面白くないな」「辞めようかな」と思うことはありますか?実際に出版されたものでも、途中で挫折しそうになった経験はありますか?
A. ありますね。特に、見切り発車で書き始めてしまったものは、うまくいかないことが多いです。「締め切りが迫ってるからとりあえず書いちゃおう!」みたいな時に、ちゃんと設計図を立てずに進めると、「あれ、うまく立ち上がらなかったな……。」ということも。
もちろん「とりあえず書き終えるほうが良い」という考え方もあるのですが、難しいところです。
―設計図があれば、多少うまくいかなくても、最初に立ち返ったり、脱線しても面白くなることもあるのでしょうか?
A. そうですね。最初にしっかりと設計図を立てておくことは、とても大切だと思っています。
Q. 自分の色を出しつつ、読みやすい形で人に読んでもらうにはどうすればいいのでしょうか?
A.「人に読んでもらう」という観点では、「自分らしさ」にこだわりすぎるのは、かえって難しくなることもあります。
一つの方法としては、まずは「自分らしさ全開」で書いてみて、それを翌朝「他人の目」で読み直してみること。まったく情報を知らない他人になったつもりで言葉を足したり、表現を変えてみたりする。そうやって俯瞰的に見る訓練が大切だと思います。
おわりに
講座後には参加者から「論文作成に活かしたい」「就職活動のES作成の参考にしたい」「書くことだけでなく、話すときの言語化についても興味がわいた」といった声が寄せられました。
京都学生広報部も今回学んだことを活かし、これからさらに“伝える力”を磨いていきたいと思います。
三宅香帆さん、貴重なお時間と学びの機会をありがとうございました!
(京都女子大学 現代社会学部 竹原亜月)